058-393-0111
お問い合わせ
婦人科
診療科の特色
私達は患者さん本位の治療、患者さんに優しい医療が最も大切であると考えています
- 患者さんとの会話を大切にします
- 患者さんに安心して診療を受けていただけることを大切にします
- 患者さんに心から納得して診療を受けていただけるよう十分に説明することを大切にします
診療科のPR
子宮摘出手術のデメリットとは?
羽島市民病院婦人科は、長年、子宮筋腫や子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術を診療の主体としてきました。
平成24年から令和6年までの13年間で558件の全腹腔鏡下子宮摘出術、172件の腹腔鏡下子宮筋腫摘出術、382件の腹腔鏡下子宮内膜症手術を施行しています。
特に子宮摘出に関しては、”子宮を摘出すると女ではなくなってしまうのでは”と手術を躊躇する患者さんが時にみえましたが、子宮を摘出しても女性らしさが変わることは無いこと、開腹手術に比べて腹腔鏡手術は傷が小さく負担が軽いことなど、腹腔鏡手術のメリットについて時間をかけて説明することで、多くの患者さんには納得して手術を受けていただけたものと思っています。
私自身も腹腔鏡手術は患者さんにとって最良の治療法であると心から信じていました。
ところが、この数年、立て続けに子宮を摘出することによるデメリットを示す論文が発表されました。
要点としては、子宮を摘出すると卵巣への血流が減少する結果、卵巣機能が悪化して早期に閉経状態となると報告しています。
卵巣は子宮の両脇にあり、排卵がおこるところということは多くの方がご存知だと思います。
より重要なのは排卵に伴って女性ホルモンを産生する臓器だということです。女性ホルモン ; エストロゲンは女性が女性らしくある上で必須のホルモンですが、それ以外にもアンチエイジング作用、骨量を保つ作用、悪玉コレステロールを抑え、血管の働きを維持することで動脈硬化を予防する作用、脳の血流を安定化しアルツハイマー型認知症の発症を予防する効果など、女性が健康であるために非常に大切なホルモンなのです。
では、子宮摘出によって卵巣機能が悪化するとどうなるのでしょうか?アメリカの有名なメイヨ―クリニックでの研究では、子宮摘出後22年にわたり患者さんを追跡調査した結果、冠動脈疾患やメタボリックシンドロームのリスクが上昇することが報告されました。
特に35歳未満で子宮摘出手術を受けた場合にはうっ血性心不全の発症が4.6倍、冠動脈疾患の発症が2.5倍になるとのことでした。
更にはうつ病が26%増加する他、高脂血症が14%、高血圧が13%、肥満が18%、不整脈が17%それぞれ増加すると報告されました。
当然ながら両側の卵巣を子宮と同時に摘出した場合にはより強い影響が出ます。
日本では50歳前後以降に子宮を摘出する際には、卵巣に異常がなくとも将来の卵巣腫瘍の発生を予防するために同時に卵巣を摘出することが一般的でした。
卵巣の働きは50歳前後には停止するため、機能が無くなった卵巣を摘出しても弊害は全く無いだろうと考えられたためです。
ところが最近では、卵巣は閉経後にも65歳までは微量のエストロゲンを産生することがわかってきており、閉経後だからだといってむやみに卵巣を摘出することには慎重であるべきとされるようになりました。
ちなみに2023年に30~79歳の女性、302510人の女性を対象として卵巣摘出の影響を調べた研究では、両側卵巣摘出により心血管疾患発症リスクが19%増加すると報告されています。
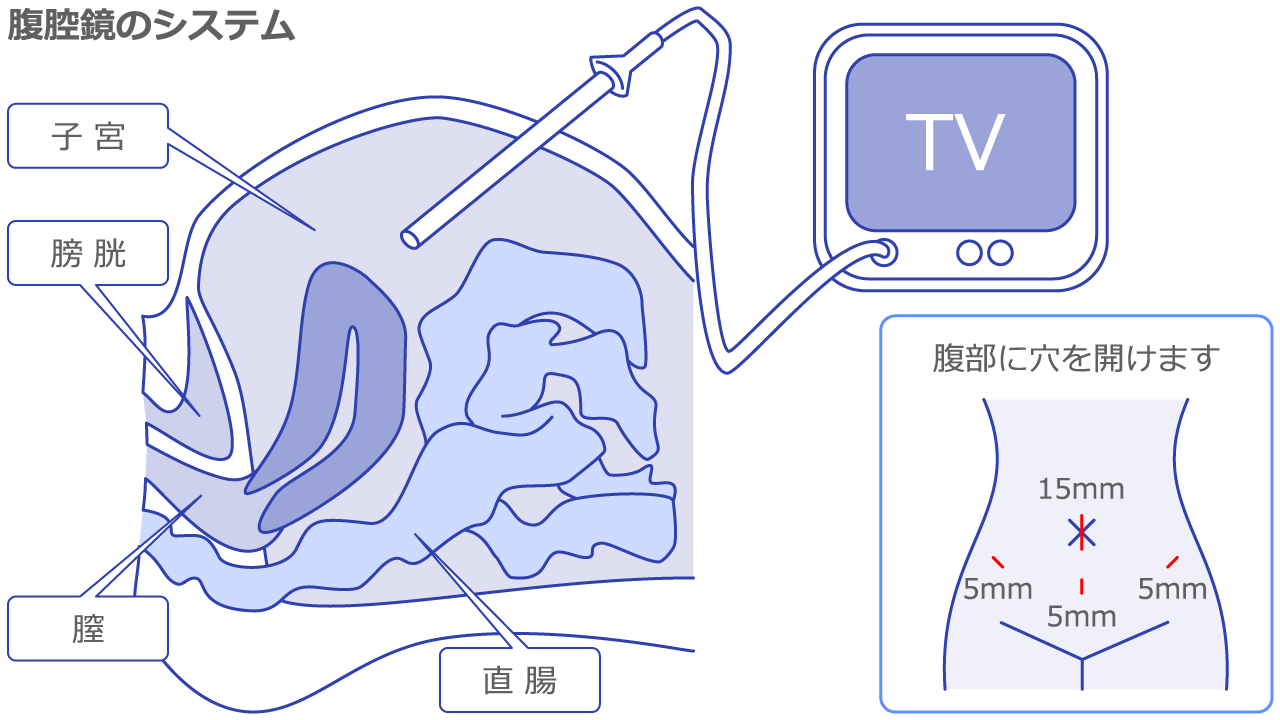
ホルモン療法のすすめ
子宮筋腫や子宮内膜症は女性ホルモン ; エストロゲン依存性の疾患であり、エストロゲンによって病気が進行したり悪化したりします。
逆にエストロゲンが無いような状況、例えば、更年期になると、エストロゲンが減少する結果、子宮筋腫や子宮内膜症は改善します。
この事実を応用した治療がホルモン療法です。
ホルモン療法により卵巣の働きを一時的に抑えて、人工的に更年期状態に導くことにより、筋腫や内膜症の病巣が縮小します。
また、治療中は生理が止まるため、過多月経や生理痛などの生理に関連した症状も改善します。
一方、更年期状態になる治療であるため、副作用として更年期症状が出ることがある点が欠点です。
典型的なのがhot flash(のぼせ)で、首から上が急にカーッと火照るような症状が出ることがありますが、これまで大勢の患者さんにホルモン療法を受けていただいた私の経験からすると日常生活に強い影響が出るほどの症状が出ることはほとんど無いと考えています。
もちろん、更年期症状を和らげる治療 ; 漢方薬などがありますのでどうかご安心ください。
さて、先ほどはエストロゲンが減少した状態が長期になると冠動脈疾患やメタボリックシンドロームが増加する可能性があると言いましたね。
ではホルモン療法の場合はどうなのでしょうか?
ホルモン療法により長期間、エストロゲンが減少した状態になると、当然ながら同様の弊害が発生するリスクがありますが、実は日本ではホルモン療法はどんなに効果があっても6か月で一旦終了しなければならないという決まりがあるのです。
従って、ホルモン療法により冠動脈疾患やメタボリックシンドロームが増加するといった心配はありません。
では、なぜ6か月で中止しなければならないかというと骨への悪影響が出る可能性があるからです。
女性の骨にとっても、エストロゲンは大変重要で、エストロゲンが減少した状態が6か月以上続くと、骨量が減少し始めることがわかっています。
子宮筋腫や子宮内膜症に対してホルモン療法はとても有効ですが、たった6か月で治療をやめなければならない⋯これがホルモン療法の最大の欠点かもしれません。
この欠点を解決する方法として海外ではホルモン療法に丁度、更年期障害の時に処方されるような少量のエストロゲンを併用するやり方(アッドバック療法といいます)が行われています。
少量のエストロゲンを併用することでhot flashのような副作用は軽減しますし、何より骨量が維持されるため長期間のホルモン療法が可能となり、海外では手術療法よりホルモン療法を行うことが第一に推奨されるようになってきています。
一方、日本ではアッドバック療法は未だ認められていないため、他の方法を選択せざるを得ないのが現状です。
当科ではホルモン療法を6か月間施行した後に黄体ホルモンに変更する方法をおすすめしています。
黄体ホルモンを内服することにより、引き続いて無月経状態が続くため、過多月経や生理痛などの症状を長期間コントロールすることが可能です。
ホルモン療法と異なり、更年期状態になるわけではないのでhot flashや骨量減少などの副作用の心配はほとんどありません。
一方、黄体ホルモンを服用中は理論的には生理はきませんが、特に服用が長くなると不正出血が起こることがある点が欠点です。
万が一、出血が増量した場合には、前回のホルモン療法から6か月以上時間が経っていれば、ホルモン療法を再開することがが可能です。
子宮筋腫や子宮内膜症に有効なサプリメントがあります
エストロゲン依存性疾患である子宮筋腫や子宮内膜症に対しては上述したホルモン療法が非常に有効ですが、骨に対する悪影響から長期間施行できないことが欠点です。 一方で子宮筋腫も子宮内膜症も閉経までは悪化する可能性があるため、長期間にわたり安全に投与できる薬があればより理想的ですよね。 実は子宮筋腫や子宮内膜症に対して有効性が確認されているサプリメントがありますので幾つかご紹介いたします。
1. ビタミンD
ビタミンDは骨を作るうえで重要な脂溶性ビタミンです。 最近はビタミンDには骨への作用以外にも様々な細胞の増殖や免疫システムへの作用があること、抗菌作用、抗炎症作用、抗がん作用などがあることがわかってきました。 子宮筋腫においては、女性ホルモン受容体の数を減少させてエストロゲンの効果が出にくくする他、筋腫細胞内で異常に亢進している細胞内シグナルを減少させる結果、細胞の増殖を抑制することがわかっています。 ビタミンDはほとんどが日光(紫外線)への暴露によって皮膚で産生されるホルモンですが、近年は美容的に紫外線を避ける女性が増加している結果、ビタミンD不足が社会的にも問題になっています。 子宮筋腫の患者さんで、採血によりビタミンD不足があることが判明した場合にはビタミンD摂取がお勧めです。
2. ウコン(クルクミン、ターメリック)
ウコンはしょうが科ウコン属の多年草で、インドが原産です。 カレーに使用される香辛料の一つといった方が有名かもしれません。 実はウコンは子宮内膜症に対する効果が最も研究されているサプリメントなのです。 ウコンは内膜症の発症や進展に大きな役割を果たしているNFKBという因子の働きを抑制することにより内膜症に対する治療効果を発揮します。 ウコンを実際に臨床応用したところ、生理痛・性交痛・慢性骨盤痛が改善したことが報告されています。
3. 抗高脂血症薬 ; リピトール
リピトールはサプリメントではありませんが、高脂血症を治療する薬剤として長年使用されてきた薬です。 子宮筋腫に対しては、筋腫細胞で作用が亢進しているWnt/βカテニン経路を抑制することにより、子宮内膜症ではNFKB経路を抑制することにより治療効果を発揮します。
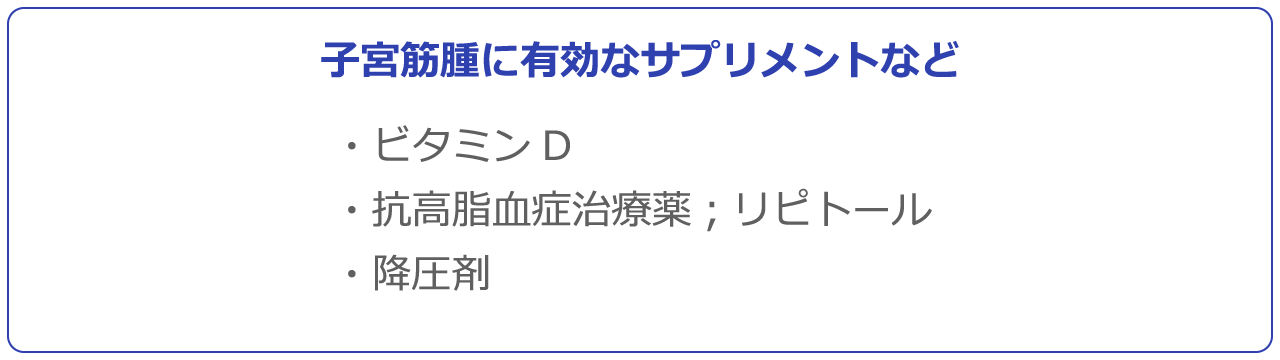
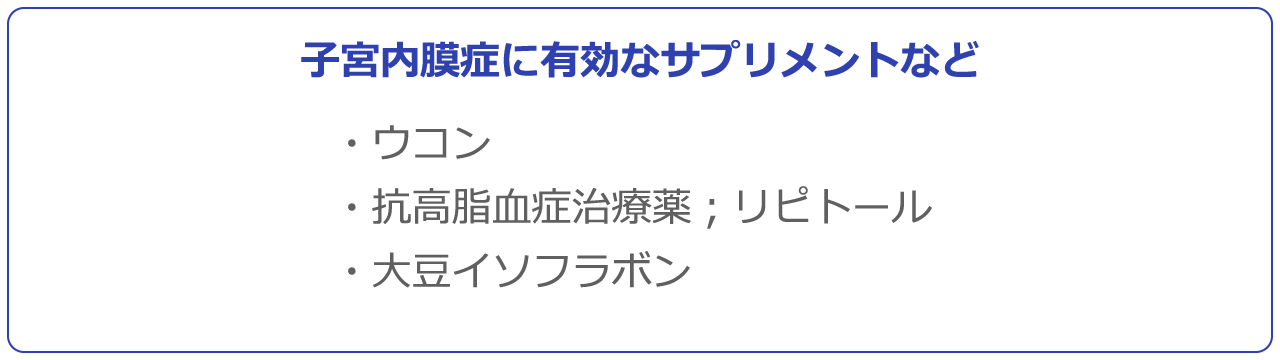
文責:婦人科医師 久保真
スタッフ

- 日本産婦人科学会専門医
- 日本産婦人科学会
- 日本産婦人科内視鏡学会

愛知医科大学病院
感染症科
感染制御部教授 三鴨 廣繁
- 日本感染症学会感染症専門医・指導医
- 日本産科婦人科学会専門医・指導医
- 日本東洋医学会専門医・指導医
- 日本真菌学会認定専門医
- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター
- インフェクションコントロールドクター
- 抗菌薬臨床試験指導者
- 母体保護法指定医
- 外科周術期感染管理認定医・教育医
- 日本化学療法学会抗菌化学療法認定医・指導医
- 日本性感染症学会認定医
- 日本感染症学会
- 日本産科婦人科学会
- 日本化学療法学会
- 日本環境感染学会
- 日本性感染症学会
- 日本臨床微生物学会
- 日本外科感染症学会
- 日本細菌学会
- 日本医真菌学会
- 日本臨床検査医学会
- 日本東洋医学会
- 日本母性衛生学会
- 日本周産期・新生児医学会
- 日本思春期学会
- 日本手術医学会
- 日本呼吸器学会
- 日本結核・非結核性抗酸菌症学会
- 日本TDM学会
- 日本嫌気性菌感染症学会
- 緑膿菌感染症研究会
- 日本クラミジア研究会
- 岐阜大学医学部附属病院
- 岐阜県立下呂温泉病院
- 岐阜県厚生連中濃総合病院
- 愛知医科大学病院

岐阜大学医学部附属病院
成育医療・女性科 古井 辰郎
- 日本産科婦人科学会認定・産科婦人科専門医・指導医
- 日本生殖医学会認定・生殖医療専門医・指導医
- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター
- 日本産科婦人科学会
- 日本生殖医学会
- 日本がん・生殖医学会
- 日本受精着床学会
- 日本生殖内分泌学会
- 日本IVF学会
- 日本生殖心理学会
- 日本内分泌学会
- 日本癌学会
- 日本婦人科腫瘍学会
- 日本癌治療学会
- 日本婦人科乳癌学会
- 日本女性医学学会
- 日本周産期新生児医学会
- 岐阜大学医学部附属病院 研修医
- 県立岐阜病院 研修医
- 岐阜大学医学部附属病院 医員
- 米国テキサス大学MDアンダーソン癌センター 研究員
- 岐阜大学大学院 助手 講師 准教授 臨床教授
- 岐阜大学医学部附属病院 教授
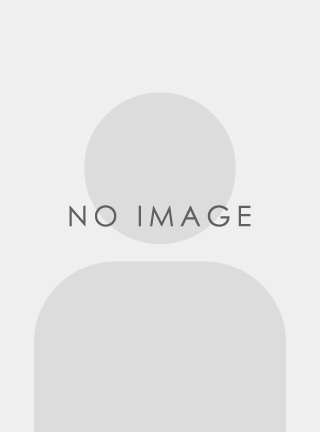
岐阜大学医学部附属病院
産婦人科 上田 陽子
キーワード
- 腹腔鏡手術
- 子宮筋腫
- 子宮内膜症
- 子宮内膜症再発予防
- 黄体ホルモン抵抗性
- 黄体ホルモン療法


